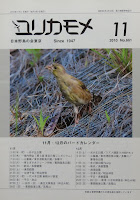その小石川植物園では“キガオヒヨドリ” 【写真・下】の群れを見かけました。もちろんそんな名前のヒヨドリがいるわけではなく、ツバキの花に顔を突っ込んで、その花粉を大量につけて顔が黄色くなったヒヨドリです。彼らの行動を見ていると花の蜜を吸うだけではなく、花びらを食べています。そのため大量の花粉が顔につくようです。かつてはどうだったかと思い起こすと、以前から嘴付近が黄色個体は見ていましたが、顔までは少なかったような気がします。いかがでしょうか。
ところで、“ヒヨドリの行動が昔と違う” という話は以前からありますが、その実態はまだ詳しくは調べられていません。ヒヨドリはいま日本では一番の“普通種”といえる鳥ですが、世界的に見れば、その分布はほぼ日本だけといえるほどです。我が国での本格的な研究を行う必要がありそうです。しかし、なかなか手ごわそうですね。 〔研究部・川内博〕